
「みんなと仲良く」「人の気持ちを考えて行動しなさい」子どもの頃から、協調性を大切にするように教えられてた日本では「自分の意見をはっきり言うのはわがまま」と受け取られることがあります。
その結果、「自分の意見を言わない人」が一定数存在し、社会ではそれが問題視されることもあります。とくに職場やチームで活動する場面で、自分の意見を言わない人が「ずるい」と感じられることがあります。
「なぜ自分だけが責任を背負って意見を言わなきゃいけないの?」「黙っている人のほうが楽をしていない?」そんなモヤモヤを抱えた経験、ありませんか?
この記事では、「自分の意見を言わない人はずるい」と思われる理由を深掘りしつつ、意見が言えない人の心理背景や、どうすれば発言力を身につけられるのかをわかりやすく解説します。
自分の考えをしっかり言えるようになるヒントが満載なので、ぜひ参考にしてみてください。
「自分の意見を言わない人はずるい」と感じる理由とは?
職場や日常生活で「この人、いつも黙ってるけど、それってずるくない?」と感じたことはありませんか?ここでは、その“ずるさ”の正体を3つの視点から解説します。
責任を回避しているように見える

自分の意見を言わない人は、決定や判断の場面で発言を避けがちです。その姿勢は、「自分だけ責任を取りたくないのでは?」と周囲に映ってしまいます。
たとえば会議などで「どっちでもいいです」「皆さんの意見に従います」と言う人は、発言した他のメンバーよりもリスクを背負わずに済みます。そのため、「責任逃れしている=ずるい」と感じさせてしまうのです。
周囲に合わせて得をしているように感じる
自分の意見を言わない人は、多くの場合、周囲の空気や流れに合わせて立ち回ります。一見、協調性があるように見えますが、実際には自分の立場を明確にしないことで、あらゆる場面で“都合のいいポジション”を取っているようにも感じられます。
結果として、「損をしない立場でうまくやっている」「自分だけ楽をしている」と受け取られ、「ずるい」と思われる要因になってしまうのです。
後出しで否定してくることがある

最も不快に感じられるのが、自分では最初に意見を出さなかったのに、結果が出た後で「だから言おうと思ってたんだよね」と後出しで否定してくるケースです。
こうした態度は、最初に意見を出してリスクを取った人にとっては非常に不公平に感じられ、「意見を出さずに安全圏から批判だけするなんて、ずるい」と強い不信感を抱かせる原因になります。
なぜ自分の意見を言わないのか?その心理背景
「自分の意見を言わない人」に対して「ずるい」と感じる場面は多くありますが、実は本人にとっても“言えない”ことが悩みになっていることがあります。ここでは、自分の意見を口に出せなくなる5つの心理的な理由を解説します。
否定されるのが怖い

自分の意見を言わない人の多くは、「否定されるのが怖い」という不安を抱えています。とくに、自分に自信がない人ほど、意見を否定されたときに「人格を否定された」と感じてしまいがちです。
しかし、意見が否定されることは人格の否定ではありません。これは切り離して考えることが大切です。意見を交わすことは、より良い結果を導くためのプロセスであり、あなたの考えに反応があったというポジティブなサインともいえます。
まずは、「否定=悪いこと」という思い込みを手放しましょう。
人と対立したくない
意見を言わない理由として「人と争いたくない」という気持ちを挙げる人も多いです。日本では“空気を読む”文化が重視されるため、意見をぶつけることが「和を乱す」と思われがちです。
しかし、意見を交わすことと争うことはまったくの別物です。むしろ、相手に自分の考えを伝えることで、相互理解が深まり、人間関係の信頼を築くことにもつながります。「争いを避けるために黙る」のではなく、「関係性を築くために伝える」という視点を持ちましょう。
間違っていたら恥ずかしいと感じる

「自分の意見が間違っていたらどうしよう」「笑われたら嫌だ」そう感じることは自然ですが、意見に正解・不正解はありません。意見とは、あくまでその人の考えや立場を表すもの。
多様な視点があること自体が議論を豊かにし、価値を生むのです。「完璧な答えを出さなきゃ」と力まず、まずは自分の視点を共有するところから始めてみましょう。
自分の考えが整理できていない
意見を言えない理由のひとつに、「そもそも自分の考えがまとまっていない」というケースがあります。これは、普段から“自分で考える習慣”が不足していることが原因かもしれません。
また、日本では「みんなに合わせる」ことが評価される風潮があるため、あえて自分の意見を持たずにやり過ごす癖がついてしまっている人も少なくありません。
まずは、「自分はどう感じているか」「なぜそう思ったのか」を、紙に書き出すなどして言語化することから始めてみましょう。考えを整理する力は、繰り返すことで必ず鍛えられます。
同調していたほうが楽で安全だと思っている

自分の意見を言うには、ある程度のエネルギーやリスクが伴います。一方で、誰かの意見に合わせていれば波風は立ちにくく、無難にその場をやり過ごせます。しかし、同調ばかりを選ぶ生活は、自分の考えを持つ力を徐々に奪ってしまいます。
自分で考え、発信することは、仕事の成果や人間関係の構築にも大きく関わる重要なスキルです。楽な道を選び続けていると、いつか「つまらない人」と思われたり、「意見を言わない人=ずるい」と見なされたりしてしまうこともあるでしょう。
他人の意見に同調する前に、まずは「自分はどう思っているか?」を問いかけてみてください。
自分の意見を言わないことで起きるデメリット
「自分の意見を言わない人」は、一見控えめで協調性があるように見えるかもしれません。しかし、実際には発言しないことによって信頼を損ねたり、損な役回りを引き受けたりと、さまざまなデメリットがあります。
ここでは、「自分の意見を言わないこと」が引き起こす具体的なリスクを3つ解説します。
周囲から「ずるい」と思われる

何も意見を言わずに黙っている人に対して、「責任を取りたくないんだろう」「批判されたくないから黙っているんだな」と感じる人もいます。とくに、意見が求められる場面で一切発言をしないと、「自分だけ安全な立場にいようとしている=ずるい人」だと思われてしまう可能性があります。
また、議論の場では他人の意見にはノーコメントだったのに、後から「私はそう思わなかった」と発言すると、「後出しで言うなんて卑怯」と捉えられることも。発言をしないことでその場は穏便に済んだとしても、結果的に評価や人間関係に悪影響を与えるリスクがあるのです。
信頼を得にくくなる
ビジネスでもプライベートでも、「何を考えているかわからない人」に対して、信頼を寄せるのは難しいものです。相手が何を思っているのか、どこに立場を置いているのかがわからなければ、本音でのコミュニケーションや意思疎通ができません。
意見を言わない人は、「受け身」「他人任せ」といった印象を与えがちです。とくに職場では、「この人に任せて大丈夫かな?」と不安に思われてしまうことも。つまり、意見を言わないことは、信頼関係の構築において大きなマイナスとなるのです。
自己主張できないことで損をする場面も

自分の意見を伝えないと、仕事や人間関係で「損な役回り」を押しつけられることがあります。たとえば、会議で誰もやりたがらない業務に名乗りを上げないままでいると、「何も言わないから反対じゃないんだろう」と判断され、望まない役割を押しつけられることもあります。
また、職場での昇進や評価の場面でも、「自分の考えを持っていない」「リーダーシップがない」と見なされ、チャンスを逃すことにつながりかねません。自分の意見をきちんと伝えることは、自分の立場や希望を相手に示すために欠かせない行動です。
意見を言わないことで、本来得られるはずだった成果や信頼を失ってしまうリスクがあることを理解しておきましょう。
意見を言えるようになるための思考の切り替え
「自分の意見を言わない人」がずるいと思われるのを避けたいなら、まずは考え方を変えることが必要です。意見を口に出すことに抵抗があるのは、失敗への不安や完璧主義の思考が根底にある場合が多いもの。
ここでは、意見を言えるようになるために有効な「思考の切り替え方」を3つご紹介します。
「意見=正解」ではないと理解する

まず大切なのは、「意見は正解でなければならない」という思い込みを手放すことです。そもそも「意見」とは、個人の考えや視点であって、正解・不正解のあるものではありません。
たとえば同じテーマについても、人それぞれ立場や経験が異なれば、当然異なる意見が出てくるのが自然です。それにもかかわらず、「間違ったら恥ずかしい」「反対されたら怖い」と思ってしまうのは、意見を“テストの答え”のように捉えているからかもしれません。
他人と違う意見でも、あなたの視点には価値があります。正解を出そうとするよりも、自分の考えを素直に共有することを目的にすれば、気持ちもラクになります。
結論だけでも伝えるクセをつける
意見を言うのが苦手な人は、全部を完璧に話そうとするあまり、言葉が出てこなくなることがあります。そんなときは、まず「結論だけでも伝える」ことから始めてみましょう。たとえば会議で「○○がいいと思います」とひとこと言うだけでも、自分の立場を明確に示すことができます。
理由や根拠は、あとから聞かれたときに考えてもOKです。最初からすべてを完璧に伝えようとしないことがポイント。小さな一歩でも、「意見を口に出す習慣」をつけることで、徐々に自信が持てるようになります。
知識や情報をインプットして自信を持つ

「何を言えばいいかわからない」「自信がない」と感じる人にとって、情報不足は大きなハードルです。知識や事例が頭に入っていないと、自分の考えに確信が持てず、発言を控えてしまいがち。
だからこそ、日頃からニュースや本、SNSなどで情報をインプットする習慣を持ちましょう。多くの情報に触れることで、「自分はどう思うか?」を考えるクセがつきます。そしてその積み重ねが、自信をもって意見を言える力に変わっていきます。
知識は「発言する勇気」を後押ししてくれる武器。準備ができていれば、発言への不安も自然と小さくなっていきますよ。
自分の意見を言えるようになる練習法
「自分の意見を言わない人」が「ずるい」と思われたり、信頼されにくくなったりするのを避けるためには、日頃から意識的に“意見を言う練習”をしておくことが大切です。考えを整理し、伝える力は一朝一夕で身につくものではありません。
コツコツと鍛えることで、少しずつ自分の意見をスムーズに言えるようになります。では、どのような方法で練習すればよいのでしょうか?ここでは効果的な5つのステップをご紹介します。
思ったことを書き出して整理する

まずは、頭の中にある考えを紙に書き出す習慣をつけてみましょう。書くことで、思考が視覚化され、曖昧だった考えも整理されていきます。たとえば、ニュースを見たときや会議の前などに、自分の考えをざっくりとメモするだけでもOK。
「自分はどう感じたか」「なぜそう思ったか」を言語化する練習を重ねることで、意見を即座に言葉にする力が身につきます。日記や思考ノートを活用するのも効果的です。書くこと自体が、自分の思考のクセを知る手がかりにもなります。
読書で思考力と言語化力を養う
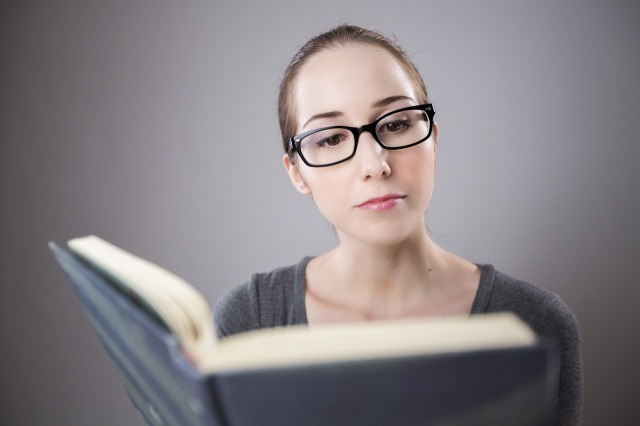
自分の意見をうまく伝えられる人は、多くの知識と表現力を持っています。それを養うには、やはり「読書」が有効です。読書は、情報をインプットしながら思考力や語彙力、論理的な構成力を養える手軽なトレーニング法。
小説・ビジネス書・エッセイなど、ジャンルを問わず多様な本を読むことで、物事への視点が広がり、偏りのない意見が持てるようになります。知識を蓄えることで、「話す内容に自信が持てない」という不安も自然と軽減されるでしょう。
自分の意見に「反論」してみる
意見を言うことに慣れていない人にとって、反論されることへの恐れは大きなハードルです。その不安を乗り越えるには、自分自身の意見に対してあえて「反論」してみる練習をするのが効果的です。
「本当にそれは正しい?」「ほかの立場だったらどう感じる?」と、複数の視点で自問自答するクセをつけてみましょう。これは、論理的思考を深めるトレーニングにもなり、自信を持って意見を述べるための土台となります。
反論を想定しておくことで、実際に意見を伝えるときにも動じにくくなりますよ。
SNSなどでアウトプットしてみる

SNSは、意見を言う練習にぴったりの場です。短い投稿文で、自分の考えや感じたことを発信してみましょう。文字数制限があるため、結論と理由を簡潔にまとめる要約力や論理力が自然と鍛えられます。
また、SNSはフィードバックが得られる点でも有効。共感されたり反応があったりすることで、「自分の意見が誰かの役に立っている」と感じる自信にもつながります。最初は日常の出来事やニュースの感想など、気軽なテーマから始めてOKです。
まず相手を肯定してから自分の考えを伝える

意見を言う場面では、「まず相手の意見を肯定する」ことを意識してみましょう。いきなり反対意見をぶつけると、相手は「批判された」と感じてしまい、議論がうまく進まなくなることもあります。
たとえば、「その考え方も素晴らしいですね。ただ私は、こういう理由で別の考えを持っています」といった形で伝えると、円滑に自分の意見を表明できます。このような言い方を習慣にしておくと、相手の気分を害さずに、自分の考えを主張する力が身につきます。
「言いたいけど言えない」という人こそ、まずはこのアプローチから始めてみてください。
「自分の意見を言わない人=ずるい」と思われないために

今回は、「自分の意見を言えない原因」とその「克服方法・練習法」について解説しました。自分の意見を言わないままでいると、周囲から「ずるい」「何を考えているのかわからない」といった印象を持たれ、信頼関係が築きにくくなってしまいます。
しかし、練習次第で誰でも意見をスラっと言えるようになります。書く・読む・反論を想定する・SNSで発信する・相手を尊重しながら伝えるなど、これらを少しずつ取り入れることで、自然に「言える自分」に変わっていけます。
自分の意見を言えるようになることは、よりよい人間関係を築くための第一歩です。今日からできることから始めて、自分の思いをしっかりと伝えられる人を目指しましょう。




